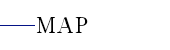みなさん、こんにちは!
5月の第2日曜といえば、、そうです母の日です!
5月の第2日曜、今年は5月11日が母の日です。
毎年やってくるとはいえ、つい直前になって「何あげよう…?」と悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。
今回は、予算別&年代別におすすめのプレゼントについてご紹介します(^^)
【予算別プレゼントアイデア】
◆~3,000円:プチギフトで気軽に
・お花(カーネーションは定番ですが、最近はスイーツみたいにアレンジされたものも人気)
・ハンドクリームや入浴剤の詰め合わせ
・おしゃれなエコバッグやキッチン雑貨など、普段使いできるアイテムも◎
◆~5,000円:ちょっと特別な気持ちを込めて
・人気のスイーツセット(地元の名店スイーツなど)
・ネックレスやブレスレットなどのアクセサリー
・アロマディフューザーなど癒しグッズや、少し高級な紅茶セットも喜ばれます。
・母の日限定のフラワーケーキやお取り寄せグルメなど、ちょっとした特別感が演出できます。
◆~10,000円以上:しっかり感謝を伝えたい!
・旅行や温泉のギフトチケット
・ブランドのお財布やバッグ
・高級グルメのカタログギフトなど、日常をちょっと豊かにする贈り物も人気です。
・最近は写真を使ったオリジナルのアルバムや動画を贈る方も増えていますよ♪
【年代別おすすめプレゼント】
・30~40代の母には、実用性とデザイン性を兼ねた家電や美容グッズが人気。
・50~60代には健康志向の食材セットやマッサージクッション、観葉植物などが◎
・70代以降は、趣味に合わせたアイテムや写真入りのオリジナルグッズもおすすめ。使いやすいシンプルなアイテムが喜ばれます。
・また、お花を育てるのが好きな方には、鉢植えのフラワーギフトもおすすめです。
【メッセージを添える】
普段はなかなか言えない「ありがとう」の気持ちを、短くてもいいので手書きで伝えてみませんか?
――――――――――
お母さん、いつもありがとう。
家族のために毎日頑張ってくれて本当に感謝しています。
たまにはゆっくり休んでね。
これからも元気でいてください。
――――――――――
メッセージカードを添えるだけで、気持ちがグッと伝わりやすくなりますよ。贈り物の中身よりも「気持ちがこもっていること」が何より嬉しいというお母さんも多いはず。特に、手書きの一言はとても心に残ります。
また、少し照れくさいという方は、家族写真を添えたり、日頃の出来事を手紙形式でまとめたりするのも良い方法です。時間をかけた分、気持ちがより一層伝わります。
一緒にお出かけするだけでもお母さんは嬉しいのではないでしょうか?
宜しければ当店にいらしてください(´∀`)
素敵な母の日になりますように。